講師紹介
担当講師
- 担当曜日で絞り込む
-

younoki
Yunoki
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
東北芸術工科大学卒業
中学校専修免許(美術)
高等学校専修免許(美術)
中学校専修免許(美術)
高等学校専修免許(美術)

あっちゅん
Acchun
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
大阪総合デザイン専門学校
コミックアート学科卒業
コミックアート学科卒業

たぬやま
Tanuyama
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
筑波大学芸術専門学群卒業
高校教諭第1種免許(美術、工芸)
高校教諭第1種免許(美術、工芸)

仁平春希
Nihei Haruki
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
女子美術大学短期大学部
専攻科造形専攻
創造デザインテキスタイル専攻卒業
中学校教諭二種免許状(美術)
専攻科造形専攻
創造デザインテキスタイル専攻卒業
中学校教諭二種免許状(美術)

サトウナギサ
Sato Nagisa
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
女子美術大学デザイン工芸学科
ヴィジュアルデザイン専攻卒業
ヴィジュアルデザイン専攻卒業
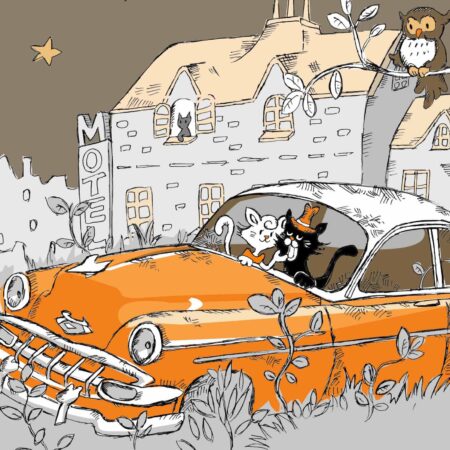
戸田ゆうか
Toda Yuka
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
名古屋造形芸術短期大学
ビジュアルデザインコース卒業
ビジュアルデザインコース卒業

ふじた
Fujita
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
学校名非公開

あゆ
Ayu
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
大阪芸術大学短期大学
デザイン美術学科卒業
デザイン美術学科卒業

ちたた
Chitata
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
大阪デザイナー専門学校
プロダクトデザイン学科卒業
プロダクトデザイン学科卒業

s1n
Sin
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
札幌市立大学 デザイン学部卒業

鳥虫透
Torimushisuki
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
学校名非公開

もねお
Moneo
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
学校名非公開

璃沢ゆと
Risawa Yuto
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
名古屋造形大学卒業

西宮
Nishimiya
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
学校名非公開

ごえん
Goen
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
武蔵野美術大学造形学部
油絵学科版画専攻卒業
油絵学科版画専攻卒業
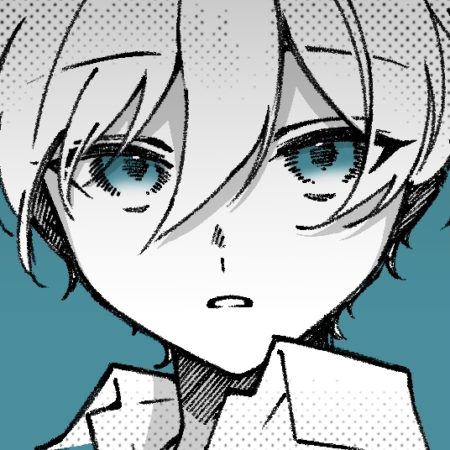
よみやみなと
Yomiya Minato
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
札幌市立大学
デザイン学部デザイン学科卒業
デザイン学部デザイン学科卒業

のず
Nozu
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
大阪総合デザイン専門学校
コミックアート学科卒業
コミックアート学科卒業

おおしま
Oshima
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
女子美術大学
ヴィジュアルデザイン専攻卒業
ヴィジュアルデザイン専攻卒業

生田月恵
Ikuta Tsukie
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
女子美術大学芸術学部
美術学科卒業
美術学科卒業

けにゃ
Kenya
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
京都芸術大学
キャラクターデザイン学科卒業
キャラクターデザイン学科卒業

砂森
Sunamori
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
多摩美術大学美術学部
グラフィックデザイン学科在籍
グラフィックデザイン学科在籍

こはる
Koharu
- 月
- 火
- 水
- 木
- 金
- 土
町田建築&デザイン専門学校
コミックイラスト科卒業
コミックイラスト科卒業
無料体験レッスン
ATAM ACADEMYの
カリキュラムを体験できる
オンライン無料体験レッスンを毎週開催
カリキュラムを体験できる
オンライン無料体験レッスンを毎週開催

オンラインコースでは、PCで講師とビデオ通話をしながら授業を進行していきます。iPadに必要なソフトをインストールし、apple pencilを使って授業を行っています。課題や制作した作品は講師とチャットやメールでやりとりをすることで共有を行います。
兄弟でのご参加、お友達同士のご参加もOK。
オンラインであっても、対面型の教室と同じように学ぶことができます。
- 費用 無料
- 時間 60分
- 人数 1対1
- 場所 全国可
受講に必要な機材
通信用デジタル端末
インターネット・カメラ機能のある端末1台
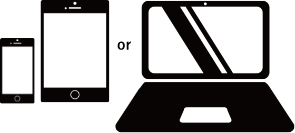
描画用デジタル端末
タブレット&タッチペン

紙とペン
でも
参加OK!
でも
参加OK!
現役のクリエイターが教えます!
-
 すぴかSupika
すぴかSupika -
 水卜Miura
水卜Miura -
 久遠Kudou
久遠Kudou -
 茉莉絵Marie
茉莉絵Marie
iPad・Apple Pencil
初月無料レンタル実施中!
無料体験申込みはコチラから
初月無料レンタル実施中!