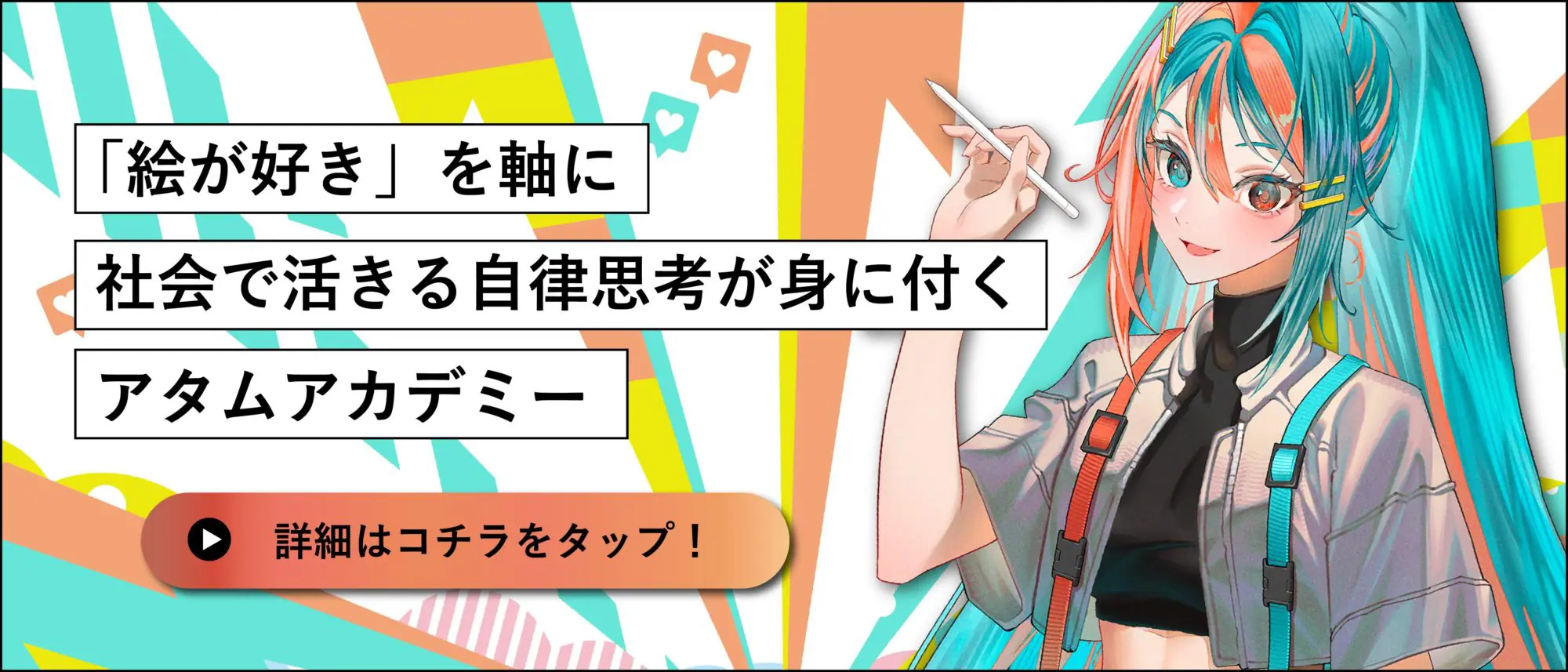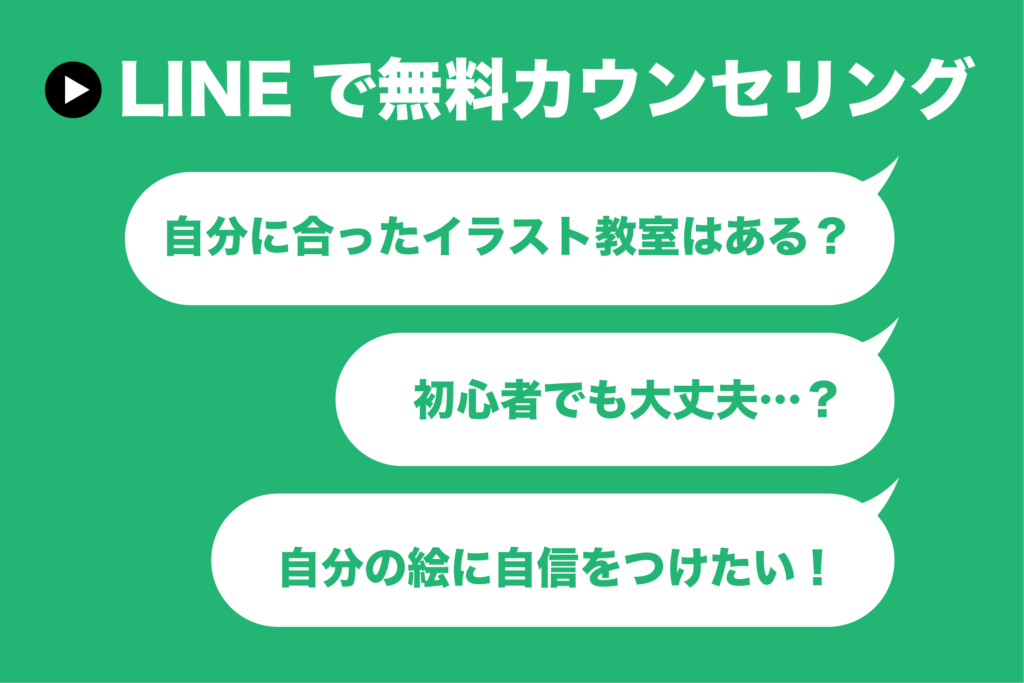美術教師になるには?進路や勉強するべきこと

今回は、美術の教師になりたい人のために勉強するべきことや進むべき進路ついて解説していきます。解説してくれる生田月恵先生は、アタムアカデミーの講師として勤める前は、美術大学卒業後、中学校及び高校で美術科の教員をしていました。
美術教師の仕事の概要
「美術の授業の目的って、アートが上手になるための勉強をすることじゃないの?」と思っている方が多いかも知れません。
もちろん、絵や彫刻などのアートが上手にできるようになる練習も重要です。
みなさんも、水彩画やクロッキーを授業で練習したことがありますよね?
けれども、美術の授業で大切なのはそれだけではありません。
学校で教える美術の大切な目的は、「アートや芸術、美しいものを見る・感じる力を養うこと」「絵や立体造形、色や表現技法を学び、表現する力を育てること」というものがあります。
「絵の上手さや作った作品のかっこよさ」という「自分の表現を発信する力」だけではありません。
「素敵なものを見つけることができる、丁寧に物事を観察することができる」という「見る力、感じて受け取る力」も育てるのが美術の授業の役割です。
授業を考えるために美術教師は日々、使えそうなアイデアを探したり、新しい絵の具の使い方や道具を見つけてみたり、子供たちが驚きそうな世界中の面白い作品を探したりします。そうやって「アートのアンテナ」を伸ばして、身近なものから外国のものまでアートを見ることで、授業のための知識を蓄えています。
また、高校の美術や、美術部の部活などは、「将来美術の大学や専門学校に行きたい」という生徒の為に、専門的な絵の技術やデッサンを教える事があります。
なので、美術の先生にも得意不得意はありますが、ある程度の美術の知識や実技の技能は必ず必要になります。
中学や高校の美術の先生の中には、「3つの学校の美術の授業だけを受け持っている」という先生もいます。
所属の自治体や学校によって、ずっと同じ学校にいたりあちこちの学校で教えていたりします。
美術教師の仕事の流れ
美術の先生の仕事は、授業の計画を立てるところから始まります。
美術だけではなく、全ての学校の先生は「生徒たちをこう導きたい」という大きな目標に従って授業の計画を作っています。
これを「学習指導要領」と言います。
美術教師のおおまかな仕事の流れは、以下のような順番です。
「目標にそったアイデアを考える」
↓
「アイデアから授業の計画を考えて準備をする」
↓
「授業をする」
↓
「目標に対して評価をする」
授業の目標にそったアイデアを考える
美術教師は授業の課題テーマを設定する上で、生徒が目標をクリアするために最適かどうかを考えます。
例えば、「想像力を豊かにする力を身につけてほしい」という目標があったら、「どんなアイデアがあったら想像力をふくらませる事ができるかな?」という考え方です。
課題テーマの例としては、家にあるペットボトルから宇宙生命体を作り出す課題・落ち葉からファンタジーの風景を作り出す課題・絵の具を飛ばしたしぶきから動物を作ってみる課題などがあげられます。
アイデアから授業の計画を考えて準備をする
目標に沿った課題のテーマを決めたら、「何回分の授業でどのくらいの進み具合になるか」計画を作り、その次に、準備をします。
みなさんに配るプリント、必要な道具や画材、何がどのくらい必要なのか、時間がどのくらいかかるか…
そういった準備です。
みなさんのお手本になるように、参考作品を自分で作ってみたり、画集などからお手本を捜してきたりもしますね。
美術の授業をする
そうして、みなさんへ授業を行い、一緒に考え、工夫したりアドバイスをしたりしながら、課題のゴールに向かいます。
授業の目標に対して評価をする
ゴールした課題を、みなさんが「目標にどのくらい近づいたか」評価をします。
その評価が、前期・後期のときにもらう通知表になってみなさんに返ってくるのです。
授業を考えるために美術教師は日々、使えそうなアイデアを探したり、新しい絵の具の使い方や道具を見つけてみたり、子供たちが驚きそうな世界中の面白い作品を探したり…
「アートのアンテナ」を伸ばして、身近なものから外国のものまであちこち見ています。
また、高校の美術や、美術部の部活などは、「将来美術の大学や専門学校に行きたい」という生徒の為に、専門的な絵の技術やデッサンを教える事があります。
なので、美術の先生にも得意不得意はありますが、ある程度の美術の知識や実技の技能は必ず必要になります。
中学や高校の美術の先生の中には、「3つの学校の美術の授業だけを受け持っている」という先生もいます。
所属の自治体や学校によって、ずっと同じ学校にいたりあちこちの学校で教えていたりします。
美術教師になるための進路
美術教師になるには、まず教員になることが必要です。
美術大学や美術系の専門学校、教育学部の美術専攻などで、美術教師になるための勉強をします。
絵や彫刻の技術はもちろんですが、美術の歴史・教育学・先生になるための教え方など…、美術だけではない様々な勉強があります。
しかし、勉強をしただけでは美術教師になれません。
様々な勉強をしながら、実際に小中学校で「教育実習」という仕事の訓練をします。
勉強と、実習をクリアして、ようやく教員免許がもらえます。
学校を出て、教員免許を取得して、試験に合格すると、ようやく先生になることができるのです。
美術教師になるために勉強するべきこと
美術教師は、美術大学で鉛筆デッサンや油絵、木彫や粘土、版画など幅広く生徒に教えるために、様々な道具の使い方について学びます。
多少の得意不得意はあっても、生徒に教えるための知識は必要になります。
絵の描き方など実技はもちろん、他にも教育に関する心理学や教育の歴史、美術の歴史も勉強も必要です。
学校では授業の作り方や教え方も学ぶことができ、一通り勉強すると、2〜3週間の教育実習で初めて教壇に立つことができます。
美術教師になるために今からできること
美術教師になるために進学を希望する場合は、少しずつ準備をしておくと良いでしょう。
ここでは3つ例を挙げてみたので、「自分でもできそうだな」ということから始めてみてください。
絵を練習し、自分の絵に自信をもつこと
自分の絵に自信が無いと、生徒にも自信をもって説明することができません。
わかりやすく説明するためにも、説得力のある絵が描けるようにたくさん練習することが大切です。
具体的には、何度もデッサンをしたり、自信をもって紹介できるような絵を完成させてみるということを試してみてください。
美術の教科書や資料集を見る
美術の教科書は、昔の作品や少し変わった絵など幅広く載っているので、なんとなく眺めているだけでもとても面白いです。
卒業しても捨てずに保管しておくといいでしょう。
地域にもよりますが、教員採用試験の問題に出てくる作品や作家はほとんど美術の教科書や資料集に載っています。
気になった作品があったら、美術館などへ実際に見に行くのもオススメです。
ボランティアやイベントに参加する
子どもとふれあうイベントや、作品展示や受付のボランティアがあれば参加することをおすすめします。
美術教師の実務に近い体験を沢山しておくと、あとで面接で話す時や履歴書を書く時にも、説得力が高くなるかもしれません。
美術教師になるための進路について、疑問を解決できましたでしょうか?
教師は授業以外の業務も多く忙しい日もありますが、大変やりがいのある職業なので、ぜひできることからトライしてみてください。
無料体験レッスン
カリキュラムを体験できる
オンライン無料体験レッスンを毎週開催

アタムアカデミーでは、入塾前にイラスト講座を体験できるオンライン無料体験レッスンを行っています。PCで講師とビデオ通話をしながら授業を体験していきます。
オンライン無料体験レッスンはiPadに必要なソフトをインストールし、applepencilを使って授業を行っています。iPadをお持ちでない方は、紙とペンでの体験もできます。
課題や制作した作品は講師とチャットやメールでやりとりをすることで共有を行います。兄弟でのご参加、お友達同士のご参加もOK。
オンラインであっても、対面型の教室と同じように学ぶことができます。
- 費用 無料
- 時間 60分
- 人数 1対1
- 場所 全国可
受講に必要な機材
インターネット・カメラ機能のある端末1台
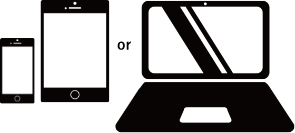
タブレット&タッチペン

でも
参加OK!
現役のクリエイターが教えます!
-
 久遠Kudou
久遠Kudou -
 すぴかSupika
すぴかSupika -
 茉莉絵Marie
茉莉絵Marie
初月無料レンタル実施中!